今回は、「家計管理や節約をしたいけど夫の理解が得られない」という方向けに書いています。
おもち家は結婚して10年。2年ほど前から本腰を入れて家計管理や節約に踏み切りました。
そのさらに3,4年ほど前から「家計のムダを減らしたい」と伝えてはいたものの、あまり理解は得られず。
 おもち
おもち「なんでそんなにお金の話ばかりするんだ」「そんな急いでガチガチにする必要ないんじゃないか」等いわれて、家計管理はそれほど進められず。
トータルで5.6年ほどかかったことになります。
今回はどうやって夫の理解を得たのか、家計管理のためにしたことを3つお話したいと思います。
家計管理と節約を夫に理解してもらうためにした3つのこと
結果からお話すると、
- お金の勉強を始めた
- 日商簿記の勉強を始めた
- 家計簿を1ヶ月だけつけてみた
この3つです。
お金の勉強を始めた
具体的に何をしたのかというと、
- 公的保障(医療費等)
- 年金
- 税金
このあたりを勉強した理由は「保険の見直しのため」。
自分で保険の見直しができるようにもなりたかったんです。
目標は夫に万が一のことがあった場合(病気や死亡等)に母一人子二人がくいっぱぐれないようにすること。
自分たちに直接関わることなので、自分でも見直せるようになりたい。と思ってのことでした。
本を読んだり、YouTubeをみたり。
本も2.3冊、YouTubeも数本みていくと言い回しや表現に違いがあれど、要点や本質的な内容はどれも同じことを伝えていると感じました。
日商簿記の勉強を始めた
お金の勉強を始めてから、日商簿記に興味を持ち、どうせなら資格も取ってしまおう!と思いたち勉強開始。
なぜ日商簿記?
日商簿記取得のきっかけは「資産」と「負債」の違いをはっきり知りたかったからです。
お金の勉強を始めた時に、本でもYouTubeでも本質的なところは同じことを伝えていると感じましたが、それが「資産と負債の違いを知っておこう」ということでした。
確かに日商簿記を勉強しはじめてから、それまで自分が資産だと思っていた「家」や「車」が実は「負債」に当てはまる場合もあるのだと知り、自分の価値観が簿記の勉強を通して大きく変わった実感があります。
FPは3級の本だけ読んだり、YouTubeを見たり。
簿記と並行でFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も勉強しました。
こちらは資格取得はせず、本を読んだのみです。
まずは1ヶ月だけ家計簿をつけてみた
お金と日商簿記の勉強を並行しながら、実際におもち家でかかる1ヶ月の出費を計算しました。
- 最低でもこれくらの生活費がかかっている
- これくらい節約できれば趣味にもお金を使える
ということを説明するためにも実際のデータが必要だと思ったからです。
具体的な数字を出すことで無駄が無いかチェックができるので、
直近の1ヶ月だけでもまずは家計簿をつけてみることをおすすめします。
知識をつけてから、事実ベースで夫と話してみた
生活費を洗い出してから夫に家計簿を見せて、
- 1ヶ月にかかる生活費は最低でもこのくらい
- 夫に万が一のことがあった場合、いくら貯めておけば生活が困窮しない
ここを2人で話し合ってみました。
もちろんこの話し合いもすんなりできたわけではありません。
なんだかんだ先延ばしにされて数回話を振ってみてやっと実現したんです。
公的保障を調べたおかげでスムーズな話し合いができた
お金の話をするときに、何で行き詰まってしまうか。
話す人同士が知識がないとそこで会話が止まってしまいます。
「また今度しらべなきゃね〜」なんて言って気づいたら数ヶ月たっているとかザラにあるので、非常にもったいないです。
たとえば、保険証が国民建国保険証なのか社会保険証なのかによって受給できる傷病手当金の期間が違ったりします。
おもち家の場合は夫が国保なので、社保よりは恩恵が薄い=もしものときの貯金は多めに必要。
こういった話をスムーズにするためにも、事前準備として万が一の際に受けられる公的な保障や補助は調べておくと良いでしょう。
車の買い替えも、事実ベースで話して納得してくれた
おもち家は昨年、私の乗っている車をミニバンから軽自動車に買い替えをしました。
- ミニバンの維持費にはいくらかかっているのか
- 軽自動車にすることでいくら削減できるのか
- 車の保険
- 車の税金
- 月のガソリン代
- 車検代
- 買い替え費用
ここも事前に金額をだしていたことで話しやすかったです。
私の車は街乗りがメインであること、高速道路はほぼ使わないこと
このあたりを加味して、軽自動車で良いという選択になりました。
安全性だったり使用条件によっては私のようにいかない方もいらっしゃると思いますので、
あくまでも一例としてご覧いただければと思います。
自分たちの叶えたいこと、それにかかる金を2人で考えてくれるように
私達夫婦はバイクが共通の趣味です。
「月◯円節約できたら、そのお金をバイクに使えるね。」
なんて話していると、夫も少しずつ節約や家計管理について協力してくれるようになりました。
明るい未来をイメージできるよう、節約をすることでこんなメリットもあるんだよ!ということをできるだけ伝えるようにしました。
「3万円浮いたらバイクのパーツが買えるね!」とか、
「2万浮かせられたらバイクの年間の保険料分だよ!」とか。
実際に浮いたお金でバイクのパーツを買っていましたが、すごく嬉しそうでした♪
まとめ:大事な話だからこそ事前に調べておこう
夫が節約に協力的じゃない。
お金の話をしようとすると不機嫌になってしまう。
過去の私がそうでした。
話をしようとしても、こちらも何から話せば良いのかわからず結局曖昧になって終わってしまいます。
お金の話をするときに大切だなと思ったのが事前準備です。
- 公的な保障(遺族年金や傷病手当金の期間や金額)
- これがないと生きていけない!という最低限の生活費
- もしものための生活費(大黒柱が病気や怪我になった場合)
このあたりをしっかり調べておくことでもしものときに役立ちますし、夫婦間で情報の共有もしやすいです。
知識がある程度付けば自信にもつながるので、「お金の管理は安心して任せてほしい!」と胸を張って言えるようになりました。
また、現状をしっかりと見ることで夫婦で同じ方向を見て進んでいける可能性も高くなります。
夫婦で向き合っていかなければならない「お金」の問題。
こまめに話し合える空気を作るためにも事前の下調べを是非行ってみてください!




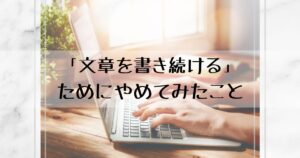



コメント